東進の共通テストリサーチは、多くの受験生が自身の進路を見定める重要なツールとして利用しています。
しかし、ネット上では「判定がおかしい」や「基準が厳しい」といった意見が散見されます。
この背景にはどのような理由があるのでしょうか?
本記事では、東進共通テストリサーチの判定について詳しく解説し、受験生が理解を深めるためのヒントをお届けします。
東進共通テストリサーチの判定がおかしい
東進共通テストリサーチの判定について、「他の予備校と結果が異なる」「成績に見合わない厳しい評価が出た」と感じる受験生がいるようです。
この理由として考えられるのは以下のポイントです。
データ母数の違い
東進のリサーチは、他の予備校と比較して利用者数が少ないため、統計的に偏りが生じる可能性があります。
例えば、河合塾や駿台・ベネッセに比べると、東進のリサーチ利用者は特定の層に集中しやすく、全体の傾向を完全に反映していない場合があるのです。
判定基準の厳しさ
東進の基準は、合格可能性50%を「C判定」とするなど、他予備校よりも厳格に設定されています。
このため、受験生によっては「判定がシビアすぎる」と感じる場合があります。
特に初めてリサーチを利用する生徒にとっては、他校との結果の違いが「おかしい」と映ることも少なくありません。
判定への過信
判定結果を絶対視する受験生が多い中で、リサーチの結果と実際の合否が異なる場合、「おかしい」という認識が広がりやすいです。
特に、志望校判定の結果がD判定以下の場合に不安を覚える生徒が多いようです。
東進共通テストリサーチの判定が厳しい理由
東進共通テストリサーチの判定が「厳しい」とされる理由には、東進独自の特徴が挙げられます。
以下に、その主な要因を解説します。
高い基準設定
東進の判定基準は、合格可能性を非常に厳格に評価する仕組みとなっています。
例えば、他の予備校では合格可能性50%が「B判定」とされることが多いですが、東進ではこれを「C判定」として分類します。
この高い基準設定により、結果的に「厳しい」と感じられるのです。
精密なデータ分析
東進は、過去の受験データを詳細に分析し、より精度の高い判定を目指しています。
これは、志望校ごとの合格者平均点や合格最低点の傾向を細かく把握しようとする試みです。
しかし、この精密さが逆に「リサーチの判定が辛い」と感じさせる原因になっている場合もあります。
データ母数の限定性
前述のように、東進のリサーチ参加者数は他予備校に比べて少ないことが多いです。
母数が少ないと、特定の成績帯に偏ったデータが全体の判定に影響を与える可能性があります。
これが、厳しい判定結果につながる一因とされています。
受験生への挑戦を意識
東進は、「少し厳しめの判定を出すことで、受験生にさらに努力を促す」という意図を持つ場合があります。
判定が甘すぎると安心感を与えすぎてしまい、最終的な学力向上に影響を及ぼす可能性があるためです。
まとめ
東進共通テストリサーチは、判定が「おかしい」「厳しい」と感じられる理由として、基準の高さやデータ母数の違い、精密な分析などが挙げられます。
しかし、これらの特徴は必ずしもネガティブな要素ではありません。
むしろ、受験生に挑戦と努力を促し、最終的な合格可能性を高めるためのシステムと捉えるべきです。
受験生は、東進の共通テストリサーチを活用する際に、他の予備校のリサーチ結果や自身の学習進度とも併せて参考にすることで、より正確な判断が可能となります。
リサーチ結果を過信せず、あくまで目安として活用することで、志望校合格に近づけるはずです。
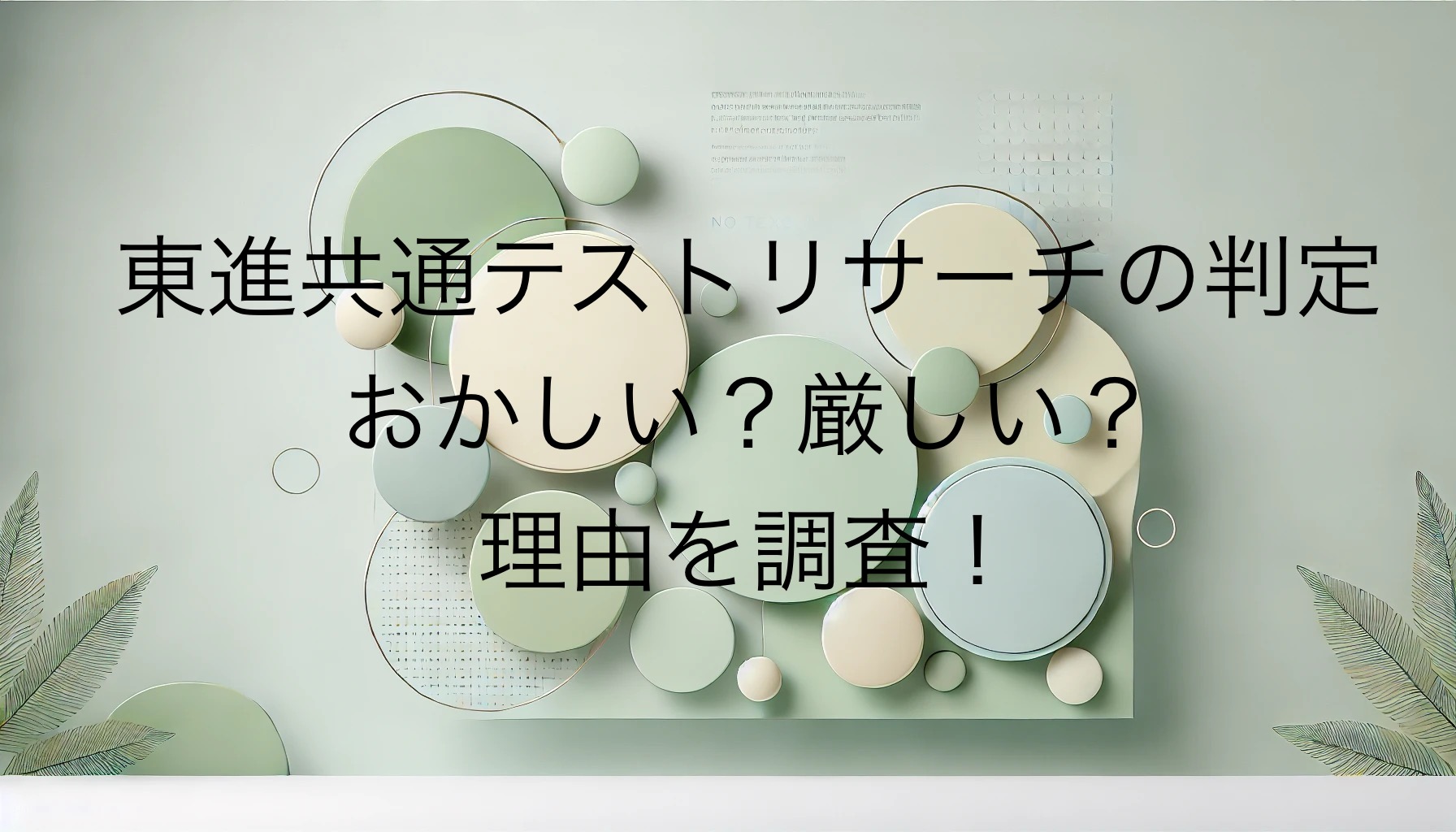
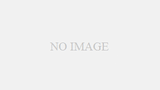
コメント